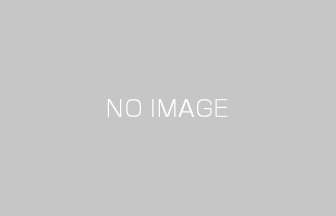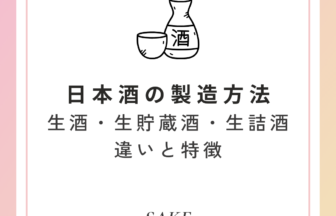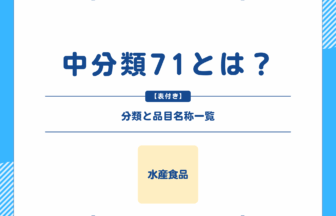肉じゃがの発祥地をめぐっては、広島県呉市と京都府舞鶴市の2都市がそれぞれ主張を展開しています。この記事では、両市の主張、歴史的背景、料理としての特徴、観光への活用、そして第三者の見解まで、豊富な資料とともに詳しくリサーチしました。
1. 起源説の比較
呉市の主張(広島県)
- 根拠と背景:明治23年に呉鎮守府に赴任した東郷平八郎の存在を根拠に、呉が発祥と主張。1997年「くれ肉じゃがの会」発足。
- 呉式肉じゃがの特徴:牛肉、メークイン、玉ねぎ、糸こんにゃく。にんじん・グリーンピースなし。シンプルな醤油・砂糖味。
- 海軍レシピとの関係:「甘煮」由来とするが、教科書現存は舞鶴のみ。
舞鶴市の主張(京都府)
- 根拠と背景:明治34年、舞鶴鎮守府開庁。東郷平八郎がビーフシチュー再現を命じたとする逸話あり。
- 舞鶴式肉じゃがの特徴:牛肉、じゃがいも、玉ねぎ、にんじん、糸こんにゃく、グリーンピースなど具材が豊富。甘酒やだしを使う家庭も。
- 海軍レシピとの関係:「海軍厨業管理教科書」に「甘煮」記載があり、発祥地と主張。
2. 料理としての特徴:呉式 vs 舞鶴式
| 比較項目 | 呉式肉じゃが | 舞鶴式肉じゃが |
|---|---|---|
| 主な具材 | 牛肉、メークイン、玉ねぎ、糸こんにゃく | 牛肉、じゃがいも、玉ねぎ、にんじん、糸こんにゃく、グリーンピース |
| 味付け | 醤油・砂糖ベース、やや薄味 | 醤油・砂糖・甘酒・だし、やや甘めでコクあり |
| 見た目 | シンプルで具材が大きめ | 具材が多く、彩りも豊か |
| レシピの再現 | 海軍レシピに基づくシンプル構成 | 教科書に基づいた忠実な再現 |
3. 明治期海軍食文化・歴史的背景
- 海軍の食事制度と肉じゃが誕生の背景:明治時代の海軍は脚気防止・栄養改善のため西洋料理を導入。洋食の再現が難しく、和風アレンジが肉じゃがとして定着したとされる。
- 東郷平八郎とビーフシチュー説:東郷平八郎がイギリスで食べたビーフシチューを再現しようとしたという逸話があるが、町おこし由来の後年創作の可能性が高い。
- 呉・舞鶴両市の海軍基地の役割:呉は明治23年に開庁、舞鶴は日本海側で唯一の鎮守府。どちらも「軍港グルメ」の発信地で、カレーなどの名物も誕生。
4. 肉じゃがの普及・町おこし・観光資源化
- 町おこしと観光資源:舞鶴は1995年に「まいづる肉じゃがまつり実行委員会」設立。記念碑やコロッケ・ジェラートなど展開。呉も「くれ肉じゃがの会」でPRを強化。
- イベント・記念碑:両市で肉じゃが記念碑が設置され、イベントも定期開催。観光客へのアピールに。
- 商標とブランド戦略:舞鶴は「元祖肉じゃがコロッケ」、呉は「呉肉じゃがカレー」などのメニュー展開で地域ブランド化を推進。
5. 第三者の見解・中立的な分析
- 研究者・メディアの分析:海軍レシピは舞鶴にしか残っていないが、教科書自体は東京編纂。発祥地の特定は難しく、論争より「文化共有の象徴」とする声も。
- 報道機関の立場:NHKや全国紙も「どちらが発祥か」ではなく「町おこしの成功事例」として報道し、中立を保っている。
6. まとめ:発祥論争の本質と文化的意義
肉じゃがは、明治期の日本海軍が健康管理と栄養改善を目的に取り入れた西洋料理から派生した和風煮物です。呉市と舞鶴市はそれぞれ発祥地を主張していますが、どちらも地域色を活かした食文化として発展し、今では観光や地域活性化の中心的存在となっています。
「ビーフシチューの再現説」や「海軍レシピの現存」など、発祥の根拠には限界があるものの、肉じゃがは日本の食卓で受け継がれ、育まれてきた“文化の象徴”といえるでしょう。