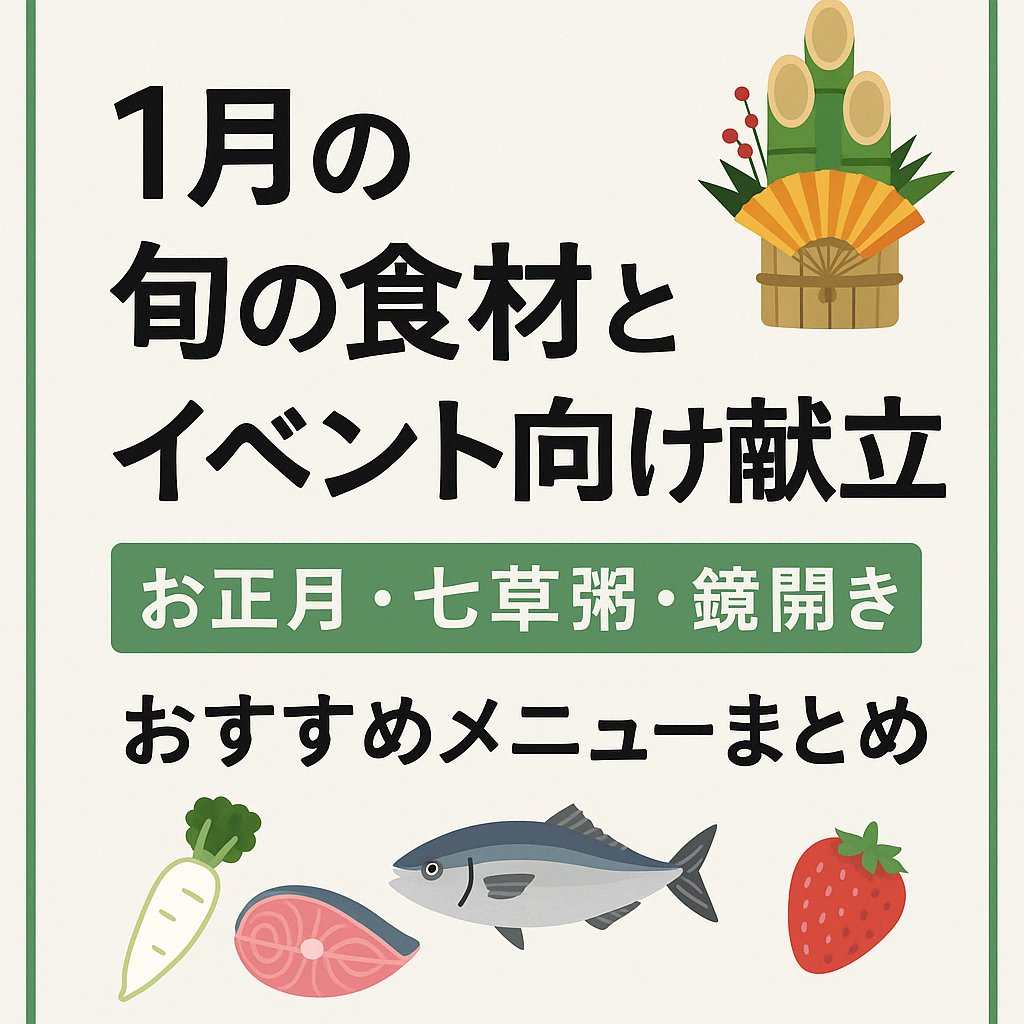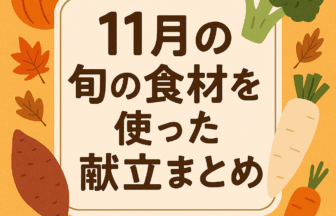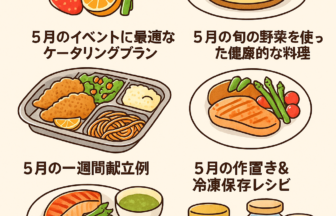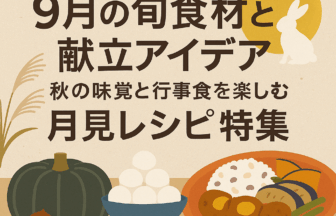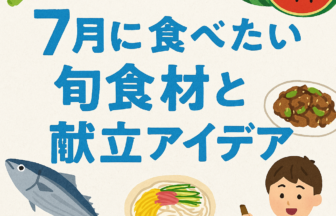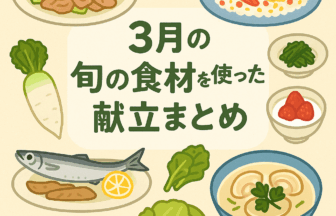1月は一年で最も寒さが厳しい時期であり、野菜や魚、果物など多くの食材が旬を迎えます。これらの食材は味が濃く、栄養価も高くなるため、体を温めたり、免疫力を高めたりといった健康面でも大きな役割を果たします。また、1月はお正月や七草粥、鏡開きなど、季節の行事食が多いのも特徴です。
1月の旬の食材一覧
| カテゴリ | 食材 |
|---|---|
| 野菜 | 大根、白菜、ねぎ、ほうれん草、小松菜、水菜、キャベツ、にんじん、カブ、れんこん、春菊、カリフラワー、さつまいも、海老芋 |
| 魚介類 | ぶり、ふぐ、たら、キンメダイ、ヤリイカ、わかさぎ、牡蠣 |
| 果物 | いちご、いよかん、レモン |
1月の主なイベントと行事食
| 日付 | 行事 | 代表的な料理 |
|---|---|---|
| 1月1~3日 | 正月 | おせち料理、お雑煮 |
| 1月3日 | 三日とろろ | とろろご飯 |
| 1月7日 | 七草の節句 | 七草粥 |
| 1月11日 | 鏡開き | おしるこ・ぜんざい |
| 1月第2月曜日 | 成人の日 | お祝い膳 |
1月の旬食材を使ったおすすめ献立例
お正月・冬のごちそう向け献立
- 主菜:ぶりの照り焼き、ぶり大根、たらとほうれん草のトマト煮、牡蠣と白菜のチャウダー
- 副菜:大根の菜飯、切り干し大根の煮物、春菊とにんじんと油揚げのごま和え、ほうれん草としめじのクリームスパゲティ
- 汁物:いか大根の煮物、かきと豆腐のすまし汁、七草粥
- ご飯もの:大根おろしと納豆のうどん、根菜と厚揚げの和風ポトフ
- デザート・果物:いちご、いちご大福、いよかん
行事に合わせた一例献立
【お正月】
- おせち盛り合わせ(黒豆、田作り、伊達巻、昆布巻き、数の子、紅白かまぼこなど)
- お雑煮(大根、にんじん、鶏肉、小松菜、餅)
- ぶりの照り焼き
- いちご
【七草の節句】
- 七草粥
- ぶり大根
- 春菊とにんじんのごま和え
- いよかん
【鏡開き】
- おしるこ(小豆、餅)
- たらと白菜の煮物
- ほうれん草のおひたし
まとめ
1月は根菜や葉物野菜、脂ののった魚、柑橘類など、寒さに耐えて栄養価が高まった旬の食材が豊富に揃います。これらを使った煮物や鍋、和え物、旬魚の焼き物や煮付けは、体を温めるだけでなく、行事食としても喜ばれます。行事や家族の集まりに合わせて、旬の味覚を活かした献立を楽しんでください。
1月の旬を楽しむ補足コンテンツ特集
1月は寒さが一段と厳しくなる季節であり、体を温める料理や、季節行事にちなんだレシピが重宝されます。ここでは、旬の食材を活かした鍋料理や行事食のアレンジ、冬の果物を使った和風スイーツなど、食卓に役立つコンテンツをピックアップしました。

1月の旬食材を使ったあったか鍋レシピ特集
寒さが厳しい1月は、体を内側から温めてくれる鍋料理が大活躍。特に旬の魚介類や冬野菜は旨味も栄養もたっぷりです。この特集では、旬の「ぶり」「たら」「牡蠣」などを活かした、冬にぴったりの鍋レシピをご紹介します。
- ぶりしゃぶ鍋: 脂がのった旬のぶりを薄切りにし、昆布だしでさっとしゃぶしゃぶ。水菜、白菜、長ねぎ、豆腐、しめじなどを合わせて、ポン酢や柑橘ベースのたれでさっぱりと。薬味は大根おろしや刻みねぎがおすすめです。
- たらちり鍋: たらの切り身と白菜、春菊、ねぎ、豆腐、しいたけなどを昆布だしで煮る定番和風鍋。たらの優しい旨味が引き立ち、ポン酢やごまだれで飽きずに楽しめます。
- 牡蠣と白菜の豆乳鍋: 旬の牡蠣と白菜、にんじん、しめじなどを豆乳ベースのスープで煮込む、まろやかでコクのある鍋。味噌を加えて味を引き締めるのもおすすめです。〆はご飯とチーズでリゾット風に。
旬の食材を使った鍋料理は、栄養価が高く、体をしっかり温めてくれるだけでなく、冬ならではの味わいを楽しむのに最適です。家族や仲間と囲む食卓に、ぜひ取り入れてみてください。
七草粥のアレンジレシピと楽しみ方
1月7日は「人日の節句」、古くから「七草粥」を食べる風習があります。春の七草(せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな=かぶ、すずしろ=大根)を入れたおかゆは、年末年始で疲れた胃腸を整えるとともに、無病息災を願う意味があります。
定番の七草粥はもちろん、食べやすくアレンジしたレシピも人気。ここでは、七草の風味を活かした現代風のアレンジレシピをご紹介します。
- 基本の七草粥: お米と水を1:5〜7の割合で炊き、刻んだ七草を仕上げに加えて軽く煮るだけ。塩味でシンプルに仕上げ、素材の風味を活かします。
- 鶏だし雑炊風七草粥: 鶏がらスープや和風だしをベースに炊き、鶏ひき肉や溶き卵を加えてボリューム感をアップ。七草は最後に加えてさっと火を通すことで、色鮮やかに。
- 洋風リゾット風七草粥: オリーブオイルとにんにく、ベーコンで風味をつけた洋風スープにお米を加え、パルメザンチーズでコクをプラス。七草は小さく刻み、仕上げに混ぜ込むだけでOK。粉チーズや黒こしょうで大人の味に。
七草粥はアレンジすることで味の幅が広がり、家族全員で楽しめる行事食になります。栄養たっぷりの七草を無理なく食卓に取り入れて、1年の健康を願いましょう。
1月の旬フルーツで作る和風デザートアイデア
1月は甘みが増したいちご、爽やかな香りのいよかん、香味豊かな柚子など、冬ならではの果物が旬を迎える季節です。これらを使った和風デザートは、おもてなしや食後のひとときにぴったり。ここでは、旬のフルーツを活かした簡単&上品なスイーツをご紹介します。
- いちご大福:
フレッシュないちごをこしあんで包み、さらに求肥でくるんだ定番和菓子。白玉粉を電子レンジで加熱して作る時短バージョンも人気。甘酸っぱさとやわらか食感が絶妙のバランスです。 - 柚子ゼリー:
柚子の果汁を寒天またはゼラチンで固めた、さっぱり味の和風ゼリー。ほんのり苦味のある果皮を細かく刻んで加えると、大人好みの上品な風味に。食後の口直しにも最適です。 - いよかん寒天:
いよかんの果肉と果汁をたっぷり使い、寒天でやさしく固めるシンプルなデザート。ほんのり甘いシロップを合わせて、果物の自然な味わいを引き立てます。見た目も鮮やかでおもてなしに◎。 - フルーツきんとん:
さつまいもペーストにいちごや柑橘系の果物を加えてアレンジ。栗きんとん風の上品な甘さに、フルーティーな酸味が加わります。見た目も華やかでお祝いの席にもぴったりです。
和風スイーツは旬の果物の持つ自然な甘みを活かすことで、余分な砂糖を控えつつも満足感のある味わいに。素材そのものの魅力を楽しみながら、季節感のある食後のデザートを演出してみてはいかがでしょうか。
冬野菜を使った常備菜・作り置きレシピ集
1月は大根、白菜、にんじん、れんこんなど、味が染みやすく日持ちのする冬野菜が豊富に出回る季節。これらの野菜は煮物・炒め物・漬物などに活用することで、毎日の食卓やお弁当を支える常備菜にぴったりです。冷蔵保存が可能な作り置きレシピを中心に、手軽に作れて栄養バランスもとれるメニューを紹介します。
- 大根のさっぱり甘酢漬け:
皮付きのまま薄切りにした大根を、酢・砂糖・塩・昆布で漬け込むだけの簡単レシピ。さっぱりとした味わいで箸休めやお弁当にもおすすめ。冷蔵で3〜4日保存可能です。 - 白菜とにんじんのごま塩ナムル:
白菜と千切りにんじんを塩もみして水気を切り、ごま油とすりごま、塩で和えるだけ。シンプルな味付けで、他のおかずと相性も良く、作り置きにも最適です。 - にんじんとツナのしりしり風炒め:
にんじんを千切りにしてツナと炒め、少量のめんつゆやしょうゆで味付け。火の通りも早く、冷蔵保存で3日程度持ちます。冷めても美味しいのでお弁当にも◎。 - れんこんのきんぴら:
れんこんは食感を活かして輪切りまたは半月切りに。醤油、みりん、砂糖で甘辛く炒め、ごまをふって仕上げればご飯が進む一品に。冷蔵で3〜4日保存可能。 - 白菜と厚揚げの煮びたし:
白菜と厚揚げをだし・しょうゆ・みりんで煮含めた優しい味わいの煮物。冷めると味が染みて美味しさがアップし、数日分の副菜として重宝します。
これらの常備菜は、まとめて作っておけば忙しい日や疲れた日にも食卓を助けてくれる心強い存在。冬野菜の持ち味を活かしながら、毎日無理なく野菜を摂れるレパートリーとして活用してみてください。
お正月明けの胃腸にやさしい1週間献立
年末年始はごちそうが続き、食べ過ぎや飲み過ぎで胃腸が疲れがち。1月上旬は、消化の良い素材を使って体をリセットする「整え献立」がおすすめです。ここでは、胃腸を労わりながら栄養をしっかり摂れる1週間の献立例を紹介します。
| 曜日 | 主なメニュー | ポイント |
|---|---|---|
| 月曜日 | 七草粥、白菜とツナの和え物、みかん | 1月7日は七草の節句。胃を休める七草粥からスタート。 |
| 火曜日 | 湯豆腐、ほうれん草のごま和え、大根とにんじんの味噌汁 | 大豆たんぱくと緑黄色野菜で胃に負担をかけずに栄養を。 |
| 水曜日 | 鶏ささみと大根の雑炊、春菊のおひたし、いちご | 鶏ささみでたんぱく補給。温かい雑炊で体もぽかぽか。 |
| 木曜日 | 鮭の蒸し焼き、白菜とりんごのサラダ、豆腐のすまし汁 | 調理油控えめな蒸し料理で胃腸のリフレッシュを。 |
| 金曜日 | 根菜と厚揚げの煮物、カブの梅和え、ご飯 | 水溶性食物繊維が豊富な根菜で腸内環境を整えます。 |
| 土曜日 | とろろご飯、焼きねぎの味噌汁、いよかん | 三日とろろの風習にならい、疲労回復にも◎。 |
| 日曜日 | 白菜と鶏団子の豆乳鍋、雑炊 | 締めに雑炊で優しい味わい。たんぱく質も補給。 |
消化によく、体を内側から温めてくれる食材を中心に取り入れたこの1週間献立は、疲れた胃腸の回復だけでなく、年明けからの生活リズムの調整にも役立ちます。無理なく食事を整えたい時期に、ぜひお試しください。