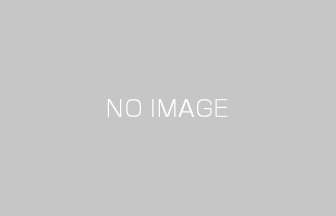お正月の食卓に欠かせないおせち料理。実は同じ日本でも、関東と関西では具材や味付けに違いがあるのをご存じでしょうか。祝い肴三種をはじめ、魚料理の種類や煮物の味付けなど、地域によって特色がはっきりと現れます。本記事では、関東と関西のおせちを比較し、それぞれの特徴を分かりやすくまとめます。
関東と関西のおせちの特徴
関東は濃い味付けや鮭などの魚料理が中心で、比較的甘めの料理が多い傾向があります。一方で関西は出汁を活かした薄味が基本で、鰤や棒鱈といった食材がよく使われます。祝い肴三種の内容も異なり、地域文化や食材の背景が色濃く反映されています。
関東と関西のおせち料理の違い比較表
| 項目 | 関東 | 関西 |
|---|---|---|
| 味付け | 濃口醤油・砂糖を多用し、濃い味 | 薄口醤油・出汁を活かした薄味 |
| 祝い肴三種 | 黒豆・数の子・田作り(ごまめ) | 黒豆・数の子・たたきごぼう |
| 甘い料理 | 栗きんとん・伊達巻(比較的甘い) | 栗きんとん・伊達巻(やや控えめ) |
| 魚料理 | 新巻鮭 | 鰤(ブリ)、睨み鯛(塩焼き) |
| 煮物 | 煮しめ(濃い味、茶色が強い) | 素材の色を活かした薄味の煮物 |
| その他の具材 | 紅白かまぼこ、きんぴらごぼうなど | 棒鱈、くわい、海老煮など |
違いが生まれた背景
関東と関西でおせちの内容が異なるのは、地域の気候や食文化、物流の発達状況が関係しています。関東では保存性を重視し、味を濃くして日持ちを良くした料理が多いのに対し、関西では出汁文化が根付き、素材本来の味を活かす薄味が好まれました。また、関西は京都を中心とした公家文化の影響で、上品で見た目も重視される傾向があります。
現代のおせちに見られる傾向
現在ではデパートや通販のおせちが全国で購入可能になり、地域差は徐々に薄れつつあります。しかし、「関東風」「関西風」として両方の特徴を打ち出した商品も多く見られ、家庭の好みに合わせて選べる時代になっています。特に祝い肴三種の違いは、おせちの文化を知るうえで大きなポイントです。
まとめ
関東と関西のおせちは、祝い肴三種の内容や味付け、魚料理に違いが見られます。関東は濃口醤油や甘みの強い料理が特徴で、鮭や煮しめが中心。一方関西は薄口醤油と出汁を活かし、鰤や棒鱈、たたきごぼうが定番です。地域ごとの背景を知ることで、おせちをより深く楽しむことができるでしょう。