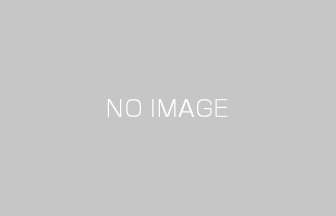おせち料理は、弥生時代の収穫祭や節供に端を発し、奈良・平安時代の宮中行事、江戸時代の庶民社会、明治時代の新暦導入、戦後の百貨店販売、そして現代の通販文化へと、時代とともに姿や社会的役割を大きく変えてきた日本独自の正月料理です。
弥生時代:稲作と節供に始まるおせちの起源
おせちの起源は、弥生時代にさかのぼります。日本に稲作文化が伝わると、季節の移り変わりや収穫に感謝する祭りが行われるようになりました。「節(せち)」とは季節の節目を表し、この日に神に供物を捧げ、収穫を祝う「節供(せちく)」の儀礼が春秋の彼岸や正月、立春、冬至など、年間を通じて営まれます。こうした節供文化こそが、おせちの最初のかたちでした。
奈良・平安時代:宮中儀式としての発展
奈良時代から平安時代には、節供が宮中行事となり「五節会(ごせちえ)」と呼ばれる最大級の祝儀料理として整備されます。元日(1月1日)、人日(1月7日)、上巳(3月3日)、端午(5月5日)、重陽(9月9日)の五つの節日には「御節供(おせちく)」と呼ばれる特別な料理が用意され、天皇や貴族が神々に供え、宴席を設けて食したと伝えられています。この「御節供」が「おせち」の語源であり、当時は重箱に詰められるものでなく、大皿や膳に盛られていました。
江戸時代:庶民への普及と重箱文化の成立
江戸時代に入ると、幕府が節日を公式の祝日に制定。御節供の文化が庶民にも広まり、年5回あった祝祭の中でも特に新年は重要視されました。これが「お正月におせちを食べる」風習のルーツとなります。また、江戸後期から明治期にかけて、祝い事の料理を保存性や華やかさ、縁起を意識して重箱に詰める形が成立し、「幸せを重ねる」という意味を込めた多段の重箱によるおせちのプロトタイプが登場します。
明治・大正時代:新暦導入と家庭教育の普及
明治時代には文明開化とともに西洋料理や食文化が流入し、都市部を中心におせちにも西洋食材やアイディアが取り入れられるようになりました。また、割烹教育が女性や主婦に普及し、女子教育の一環でおせちを重箱に詰めるスタイルや食材の組み合わせが標準化されました。新暦の採用により、正月の祝祭日やおせちを食べる時期も全国で統一されていきます。
戦後〜高度経済成長期:百貨店販売と既製品化
第二次世界大戦後、女性の社会進出や核家族化、百貨店の拡大により、おせち料理は「家庭でつくるもの」から「購入するもの」へと急速に変化します。戦後の食糧不足を背景に、家事負担を軽減しつつお祝いの食卓を華やかにするため、百貨店や料亭が重箱入りおせちを売り出し始めたのが1950年代。テレビや婦人雑誌もおせちの意味や重箱の盛り方、レシピを特集し、おせち=お正月の伝統食として日本全国に「定着」したのは、実は戦後以降の現象です。
現代:通販・多様化と新しいおせちの姿
21世紀現在、共働き世帯や単身世帯の増加、ライフスタイルの多様化によって、百貨店だけでなくコンビニ、スーパー、ECサイトでもおせちが手に入るようになりました。購入派の増加とともに、和洋折衷、中華風、ベジタリアン、地域限定品、有名シェフ監修などおせちのバリエーションはかつてなく拡大。食の多様化、世代の変化に応じて「ハレ」の料理としての本質や願いは守りつつも、時代に合った新たな形のおせちが毎年生まれています。
文化的背景と社会とのつながり
おせち料理は単なる祝い膳ではなく、日本人の「節目を祝う」「家族の絆」「無病息災や子孫繁栄の祈り」「先祖や自然への感謝」を象徴してきました。また、食文化・物流・社会構造と密接にリンクし、その時代ごとに日本人のアイデンティティや希望が重ねられてきた食文化です。
まとめ:おせちの歴史から見える日本文化
弥生時代の祀りから現代のネット通販のおせちまで、日本社会や家庭の姿が投影されてきたおせち料理。その歴史をたどることで、単なる伝統食の枠を超えた、日本人の暮らしや心の変遷が浮き彫りになるでしょう。